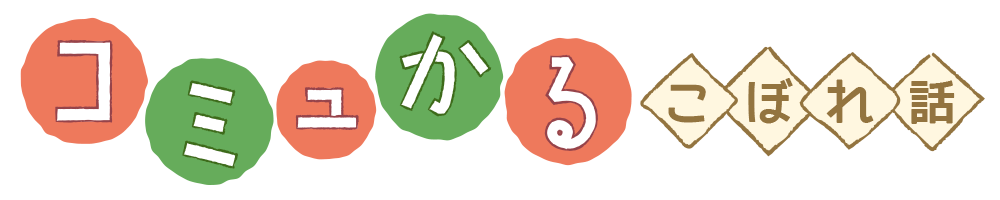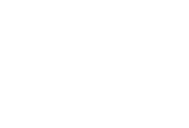 杉並ゆかりの文化人アーカイブ映像集
杉並ゆかりの文化人アーカイブ映像集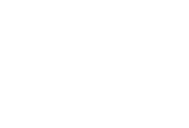 コミュかる・こぼれ話
コミュかる・こぼれ話
「コミュかる」は、「コミュニケーション」と「カルチャー」を用いた造語で、2012年に創刊した杉並区の文化・芸術情報紙です(年4回発行)。区内での公演・チケット情報や文化人のインタビューをご紹介しています。
本コーナーでは紙面には掲載しきれなかった写真や「こぼれ話」を掲載しています。
映画作家:牧原 依里さん
2025年6月21日発行「コミュかるVOL.71」

Q1:杉並にはいつから住んでいるのでしょうか。
神奈川県横浜市育ちで、3年前から杉並に住んでいます。杉並に引っ越してきた理由は、仕事が多忙で横浜の家には寝に帰るだけの生活だったことから、いっそ東京に引っ越した方が色々と便利だと思い物件を探していました。西荻窪に住む友人が、杉並はろう者が多く、とても便利だと勧めてくれたので、杉並に決めました。
Q2:杉並のどんなところが好きですか?
高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪と駅によってそれぞれ個性を感じます。私は西荻窪が好きなのですが、新しいものと古いものがうまく混ざり合っているところが好きですね。お気に入りのカレー屋さんもありますし(笑)。
Q3:映画の仕事をするようになったきっかけはなんですか。
2013年にイタリアへ旅行に行った際、たまたま行われていた、「ローマ国際ろう映画祭」に参加したことです。帰国後、映画学校へ通い始め、映画制作を学び、2016年に雫境(だけい)さんと共同監督でろう者の世界に音楽はあるのか、をテーマにした『LISTEN リッスン』というアート・ドキュメンタリー映画を作りました。これをきっかけに、フィクション映画や実験映像などの映画制作や舞台演出などに関わるようになりました。
また、日本にもろう者が繋がる映画祭が必要だと思い、2017年には東京国際ろう映画祭を立ち上げました。これは福祉施設で開催するのではなく、一般の映画館で開催することにこだわりました。なぜなら、映画館で作品を上映することで、より多くの人への周知にもなりますし、誰でも気軽に行くことができる場所で開催することで、ろう者と聴者の接点を持つ場にもなるからです。この映画祭は2年に一度の開催を目指してスタートし、コロナの影響などもあって開催できない時期もありましたが、次回開催は2025年となったときに、映画だけの上映ではなく舞台などもやりたかったので、映画祭からスケールアップした芸術祭をやってみようと思った頃に杉並へ引っ越してきました。

Q4:イタリアへのご旅行はろう映画祭が目的だったのですか?
いえ、全くの偶然です。これはろう者によくあることなのですが、現地のろう者がろう者向けのイベントがあるよ、と教えてくれることがよくあります。それで行ってみたところ、映画館で様々な作品が同時に上映されていることに驚きました。
てっきり1つの部屋での上映だと思っていたので。さまざまな映画を観ていったのですが、何の違和感もなく観ることができたんです。聴者の方が作る「手話がある映画」では、手話が間違っていたり、そんな動作や反応はしないだろう、というような違和感があり、物語に集中できないことがよくありますが、この映画祭で上映されている作品たちにはまったくそれがなかったから、内容に集中できました。観終わった後に舞台に監督が立っていて、その方がろう者だったのでとても驚いたとともに腑に落ちました。その同時に「ろう者に映画はつくれない」という固定概念が自分の中にあったことに気づいたんです。
Q5:その作品は、劇中での会話は手話でおこなわれるのですか?
はい、その国での手話です。そして英語とイタリア語の字幕がついていました。手話は万国共通ではなく、その国独自の言語を持っていますので、細かいところは判りませんが、30%はなんとなく理解することはできました。そこが音声言語とは違うところです。例えば、「飲む」という動詞は英語では「drink」と表記します。「drink」という単語を知らなければ、当然その意味もわかりませんし、推測もできませんよね。でも、手話言語では「飲む」という手話は、国が違っても、理解しやすい。もちろん、その国によって、「飲む」の手指の動きが異なりますが、視覚や動きが身体に投影しやすいものだったりすると、イメージが共有しやすいこともあり、初めて会う外国のろう者でも1週間たてばある程度コミュニケーションをとることができるんです。もちろん抽象的な話や哲学的な話は限度があり、その国の手話言語を習得する必要がありますが。

Q6:牧原さんにとって映画はどんな存在ですか?
私が小さい頃は、テレビで日本語字幕の付いた番組は数える程度しかなく、両親もろう者だったので、我が家では頻繁に日本語字幕がついている外国のレンタルビデオを利用していました。そのため、映画は私たちの日常生活の中に溶け込んでいました。
私が中高生の頃からさらに色々なジャンルの映画を観るようになりました。人生の中で影響をうけた映画はそれぞれあるのですが、映画に対する私の見方を変えた作品はミヒャエル・ハネケ監督の『ファニーゲーム』です。家族揃って観たのですが、全員目が点になりました(笑)。私はこの作品に衝撃を受けて、この作品に対しての評価をどうしたらいいのだろう、どう解釈すればよいのか、ということを、天井を見つめながらずっと考え続けていたことを覚えています。
その作品を観るまで、ハリウッド映画の中で、悪役が死んでいくことには何の感慨もなく、むしろ爽快感を感じていましたが、この作品では息苦しく、直視できない恐怖を感じました。それまで映画の中で人が死んでいくことに「悪役は死んだら爽快」「善い人が死んだら悲しい」であるべきだというラベルを貼っていたことに気付かされたんです。映画は楽しく愉快な気分にさせてくれるものが一番だと思っていましたが、そうではなくて、観た時に出てくる感情や体感そのものに全てに価値があるのだと、自分の価値観を変えるような力を持っているのだと気付かされました。
当時はまだ中高生だったので、映画制作に興味を持っていたわけではありませんが、このような経験の積み重ねが、ローマ国際ろう映画祭に参加することによって、自分の中に蓄積した思いを形にしたいと思ったのかもしれません。映画『LISTEN リッスン』は「ろう者の中に音楽はあるのか」という問い掛けを形にしたアート・ドキュメンタリー映画です。この作品をきっかけに、ろう者の音楽とは、ということを分析、リサーチするようになって約10年経ち、11月末には、これらをテーマにした、TOKYO FORWARD 2025 文化プログラムろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」にも携わります。
私はこの芸術祭を通じて、多くの人にさまざまな「新しい価値観」を体験していただきたいと願っています。もちろん、一人ひとり違っていて当たり前です。プラスでもマイナスでも、自分とは異なる価値観に触れることで生まれる体験を、ぜひ味わってほしいと思います。
プロフィール
映画作家:牧原 依里 さん
1986年神奈川県横浜市育ち。ろう者の両親を持ち自身もろう者。2016年映画『 LISTENリッスン』を雫境( だけい)氏と共同監督。 2017年に東京国際ろう映画祭立ち上げ、2022年一般社団法人日本ろう芸術協会を発足。「手話のまち 東京国際ろう芸術祭2025」総合ディレクター。
「コミュかる」は以下の杉並区役所公式ホームページでお読みいただけます。
文化・芸術情報紙「コミュかる」![]()